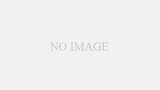ハーマン・メルヴィル (Herman Melville)の生い立ちと経歴
ハーマン・メルヴィル(Herman Melville)は、1819年8月1日にアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市で生まれました。彼の父親は裕福な商人であり、家族は厳格なカルヴァン派の信仰を持っていました。彼は4人兄弟の次男で、幼少期は家族と共にニューヨーク市内で過ごしましたが、彼の父親は破産し、家族は経済的に苦しい生活を余儀なくされました。
メルヴィルは16歳で学校を中退し、彼の最初の仕事は、ニューヨーク市の銀行での職業訓練でした。しかし、彼は海に魅了され、17歳で航海に出ました。彼は3年間の航海の後、ニューヨークに戻り、翌年航海士の資格を取得しました。その後、彼はハワイ、タヒチ、オーストラリアなど、世界中を航海しました。彼は後にこれらの経験をもとに、彼の最も有名な小説のいくつかを書きました。
彼の最初の小説『Typee』は、1846年に出版されました。彼は、パイの捕鯨船での経験に基づいて書いた、タヒチの南太平洋における自分の体験を描いたものでした。彼の次の小説『オムー・ムーラ』(1847年)も、航海経験に基づいています。しかし、彼の最も有名な作品である『白鯨』(1851年)は、アメリカの捕鯨船エセックス号の沈没に触発されたもので、この小説は今日でもアメリカ文学の傑作として高く評価されています。
しかし、メルヴィルの作品は出版されるたびに売れ行きが悪く、彼は多くの仕事を転々とすることになりました。彼は、アメリカ海軍で仕事をしていた時期があり、南北戦争中には北軍側に加わりました。戦争後、彼は再び小説の執筆に戻り、彼の最後の小説『ビリー・バッド (Billy Budd)』は、彼が死去した後の1924年に出版されました。
作家としてのハーマン・メルヴィル (Herman Melville)と作品の特徴
ハーマン・メルヴィルは、アメリカの作家であり、19世紀アメリカ文学の巨匠の1人として知られています。彼の作品には、航海や冒険、哲学的なテーマなどが含まれています。彼はまた、実験的な文学スタイルを追求し、独自の言語表現やシンボリズムを用いたことでも知られています。
メルヴィルの作品には、自然と人間の複雑な関係、人間の本性と善悪の問題、人間の苦悩や孤独など、哲学的なテーマが多く含まれています。また、彼の作品には、宗教的な要素や社会的な批判も含まれており、彼の考えや見解が反映されています。
彼の人物像については、謎めいているとされており、生涯を通じて多くの人生の試練に直面したことが知られています。彼はまた、若い頃に商船に乗り、航海や海外での経験が後の作品に大きな影響を与えたとされています。
彼の作品は、当時のアメリカ社会には理解されなかったこともあり、彼は生前にはあまり評価されませんでしたが、20世紀に入ってからは再評価され、文学史において重要な位置を占めるようになりました。
ハーマン・メルヴィル (Herman Melville)の代表作品
『白鯨』(Moby-Dick)
アメリカの捕鯨船船長が、自らが率いる船で遭遇する白いクジラ「モービー・ディック」との戦いを描いた小説です。物語は、船長イシュマエルが、同じ船に乗るアハブ船長の復讐心に燃える過激な行動に巻き込まれていく様子が描かれています。作品は、捕鯨の悲惨さや人間の限界を描きながら、哲学的なテーマや宗教的な象徴を織り交ぜた複雑な構成となっています。
『バートルビー働かない』(Bartleby, the Scrivener)
壁に囲まれたオフィスで働くスクリブナーが、一人の新人職員であるバートルビーの奇妙な振る舞いに悩まされる様子を描いた短編小説です。バートルビーは、仕事を遂行しないどころか、仕事中に「私はできません(I would prefer not to)」という言葉しか口にせず、ついにはオフィスの前で寝泊まりし始めます。作品は、現代社会における人間の孤独や脆弱性を描き、哲学的なテーマを含む深い内容となっています。
『ピエールまたはアンビバレンス』(Pierre; or, The Ambiguities)
ニューヨークの富豪階級に生まれた若者ピエールの、自分自身と社会との葛藤を描いた小説です。ピエールは、恋人との関係をめぐって家族や友人と対立し、次第に自分自身のアイデンティティを見失っていきます。作品は、個人の自由と社会の圧力の間で揺れる人間の葛藤を描き、倫理的な問題や哲学的なテーマを含む難解な内容となっています。
『ベントヴィルの戦い』(Battle-Pieces and Aspects of the War)
メルヴィルが南北戦争中に書いた詩集で、戦争の様々な側面を描いています。メルヴィルは、戦争を人間の業として扱い、戦争によって引き起こされる破壊と苦痛を表現しました。詩集は、個々の詩から構成され、戦争の現実を反映しています。
『イザイアの書』(Clarel: A Poem and Pilgrimage in the Holy Land)
メルヴィルの最後の長編詩であり、聖地巡礼をテーマにした壮大な叙事詩です。主人公クラレルは、世界を旅しながら信仰の危機に直面し、聖地での巡礼を通じてその問いに答えを見つけようと試みます。作品は、聖書に登場する物語や宗教的イメージを引用しながら、現代的な人間の苦悩や疑問を探求しています。メルヴィルは、この詩を「私の最も難解な本」として自己評価していました。
ハーマン・メルヴィル (Herman Melville)に対する評価と後世や社会への影響
ハーマン・メルヴィルは、19世紀アメリカ文学を代表する作家の1人として高い評価を受けています。彼の作品は、当時のアメリカ文学においては独自のものであり、特に20世紀以降になってからはその優れた文学性が再評価されるようになりました。
メルヴィルは、自らの作品において人間の内面や道徳的問題に着目し、現実主義文学や象徴主義文学に影響を与えました。また、彼の作品は、アメリカ文学のみならず世界文学にも大きな影響を与えており、特に『白鯨』は海洋文学の傑作として高く評価されています。
しかし、メルヴィルは生前にはあまり評価されず、作品の売り上げも低迷し、晩年は貧困に陥りました。彼が再評価されるようになったのは、死後の20世紀以降であり、現在では世界的に有名な作家の1人として認知されています。